|
内側にわがままな炎症を負って色々不安定な僕に、吹雪くん、なんて純白な心配を寄越したのは君だ。なんにも僕のことを知らない君は、困ったように眉を下げながら僕に話しかけた。 「吹雪くん、大丈夫?」 「なにが?」 「顔色、少し悪いよ?」 「そう、かな?」 「うん。」 たぶん大丈夫だよっていつもと少し違う、でもいつもみたいに隠すような笑顔の僕に、無理しちゃだめだよ、とやんわり咎める声はひどく柔らかくて優しかった。それは僕の内側の炎症に触れて、それはざわりと反応した。 「ねえ、ちゃん」 「ん?なに?」 「じゃあ、一緒にいてくれる?」 するりと口から出した言葉は、グサリと傷を抉った。ざわざわざわ、それがうるさいぐらいに叫んだ。でも僕はそれを無視した。絶対に出させてなんか、やらない。お前になんか、譲らない。 「だめ、かな?」 「ううん、もちろんいいよ!」 「ありがとう、ちゃん」 「いえいえ」 少し驚いたような君はすぐに柔らかく笑って承諾してくれた。それを内側から見てるそれは変われ変われと暴れまわる。全くもってうるさい。僕はまたそれを無視して、君に笑い返した。 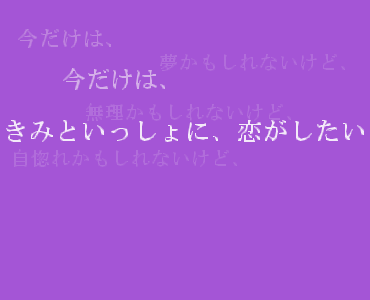
|