|
真っ白なまっしろな空間の真ん中に真っ白な君がまっしろなお花に囲まれて埋もれて眠ってた。白しろ白シロ。一面の白の中に沈む君もまた、この白たちに紛れるほどの透き通る白だった。 私はポツンと花に埋もれた君を見下ろした。君の周りで君を守るように、君を取り込むように咲き乱れたこの花は、何となく私を嘲笑っていた。私はそれを無視してぺたりと君の横に座り込んで、ぺたりと君の胸に耳を当てた。その時に見えた私の腕は嘲笑う花のように白かった。 そっと君の胸に当てた私の耳は、どうやら壊れてたみたいで、全然音が聞こえなかった。無音。私はそれが酷く悲しくて、かなしくて、ぎゅっと君を抱きしめた。 「おまえのせいだ」 突然、声が、私の頭の上から降ってきて、私はゆっくりと頭を上げた。そこには、この部屋には鮮やかすぎる赤があった。赤は、キッと私を睨んで、もう一度、おまえのせいだと吐き捨てた。 私は、真っ白な君を、鮮やかな赤のその言葉を、睨む瞳を、氷みたいに冷たい君を、全てすべて、自分の中に閉じ込めるように、そっと、そっと、目蓋を閉じた。 目蓋が閉じる、ほんの一瞬。私の右手と君の左胸が、赤よりももっともっと鮮やかな紅に染まっているのを、私は、みてみぬふりを、した。 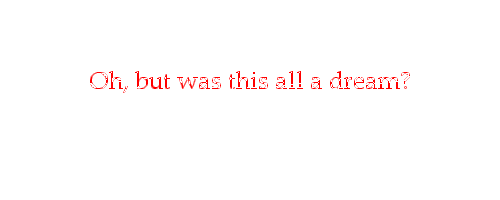 |