|
ある雨の日、私は居眠りをしてしまった。 それは結構長いもので、私が目を覚ましたときには外は薄暗くなって、HRなんてとっくに終わっていた。 誰か起こしてくれればいいのに、と心の中で愚痴を洩らしながら、私は帰宅しようと席を立った。 ずっと座ったまま寝ていたせいで、ポキリポキリと身体の色んなところの骨が快音を奏でる。 「なんや、やっと起きたん?」 「・・・っ!」 ガタン、と私が驚いたせいで足元の椅子と後ろの席の机がぶつかって大きな音をたてた。 てっきり私はこの教室には私しか居ないと思い込んでいたので、突然発生した声に私の心臓はばくばくと速く脈打つ。 声がしたほうにゆっくり振り向けば、そこには制服姿の白石くんがいた。 「おっと、そない驚くとはおもわへんかったわ。堪忍な?」 「う、うん。しら、いしくん、・・・だよ、ね?」 「そうやで、さん。それがどないしたん?」 私と白石くんだけの静かな教室と、大粒の雨音。 それは何となく不思議で、変な感じがする。 私は、白石くんとあんまり話したことがない。 たとえあったとしても、それは事務的なことぐらいだったと思う。 でも、その数回会話した時の彼と、今の彼は何かが違った。 なにが違うのかは、よく分からないけれど。 「別に、なんでもない、けど・・」 「けど?」 「え、・・け、ど・・・、何か、」 じわりじわりと、彼は私を追い詰める。 私はその圧迫感に、なんて言っていいか、なんて言い表せばいいか、わからなくなる。 でも彼は急かすことはない。ただただ、私の次の言葉をじっと待っている。 それが逆に私には急かしているように感じてしまう。 言うべきか言わないべきか、そのどちらかを選ばなければならない今、私は言うを選んだ。 というよりは、無言の圧力で選ばされたが正しい。 「その、何か、今日の白石くん、ね、変な感じがするなって・・・」 「・・・・・・」 「あ、あの、その、深い意味はなくて・・・!」 意を決して、慎重に言葉を選びながら言った私の言葉に、彼からの返事はない。 どうしよう、嫌な思いをしたのだろうか?と思い、1人で弁解していると、彼はハハッと渇いた笑いを零した。 それはどことなく、嘲笑のようで彼がするにはとても似合わないものだった。 私が彼の笑いに無言になると、彼はゆっくりと私に近づいてきた。 「さん、なんやおもろいな」 「え?」 「ほんまに、おもろい」 小さく抑えるように吐かれた言葉に、ゾッと背筋が寒くなった。 彼の表情は、影でよく分からない。 でも、やっぱり今日の彼はおかしい、と確信した。 ここから逃げないといけない。頭の中で警鐘がなる。 でも足は私の思い通りに動いてはくれなくて、その場に縫い付けられたように動かない。 「俺と、もう少し雨宿りしよか」 言いようの無い恐怖が身体の奥底から湧き出して、ひゅっ、と喉が変な音をたてた。 彼はそれを聞いて、またハハハッと渇いた笑い声を立てた。 それにあわせたように、外から眩しい光が入った。遅れて大きな地鳴りがする。 その刹那に見えた彼の表情は、私の初めてみるものだった。 光の無い真っ黒な目。不適に描かれた口元の弧。いつもとは違う、陰り。 彼は私の腰と後頭部に手を回して、ぎゅっと抱き寄せた。 窓の外から、さっきより一層大きくなった雨音と、雷鳴が私とダレカを嗤っていた。 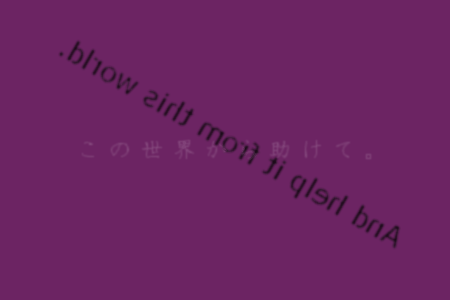
|