|
がり、君の爪がまたすり減った。 ああ、君の綺麗な手が、と少し惜しい気持ちになった。 どうしたの?何が気に食わないの?自分を責めてるの? 悔しいの?辛いの?苦しいの? 次々と私には関係のない疑問たちが生まれて消えていく。その間にも、君は爪を噛み続ける。ああ、自分を傷つけるのはやめて。 「佐久間、」 「?」 「爪、痛むよ。」 居ても立ってもいられなくて、私は君の手を握って口元から離した。ちらりと一瞬君から視線をずらして指先を見ると、案の定爪はぼろぼろに痛んでいる。吐き出しそうになる溜め息をぐっと我慢して、視線を彼の瞳にぶつけた。 「何かあるなら、些細なことでもいいから言って欲しい。」 「・・・、」 「力になんかならないけど、私は、佐久間の言葉を聞きたい。」 自意識過剰なのかもしれないけど、私の言葉にぐらりと君の瞳は大きく揺れた。戸惑い、不安、弱さが複雑に混じり合ったそれは、ゆっくりと静かに閉じられた。 私は何も言わずに、君と同じように目を閉じた。何もない暗闇の中で、今にも消えそうな小さな小さなありがとうと、手をぎゅっと握る感触を、私は君から貰った。 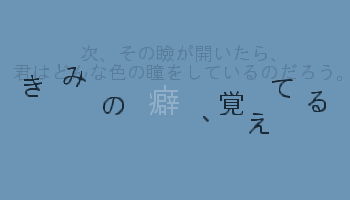
|