|
「これ、」 きらきらと雪みたいに輝く銀色の鍵を、手のひらに乗せられた。 君の温度が温く残ってるそれは、家の鍵。 「僕の家の鍵。」 どうして?と思ったけど、昔君が僕一人暮らしなんだって少し陰りのある表情で教えてくれたのを思い出した。 「、待っててよ。」 手のひらに向けてた視線が、君の声に引き戻される。 君は優しい表情をしてるのに、目は氷みたいに透き通った真剣な目。 それは久しぶりに見たせいか、私の心臓はどきりと変に鳴った。 「帰ってきたら、一番に会いに行くから。」 だから、お願い。って言われて、きゅっと包み込まれた手。 自然と私の手が鍵を握り込む形になった。 じっと君の目を見る。そこには弱い君が微かに見え隠れしていた。 「わかった、待ってる」 私が、出した答え。色々な感情が混ざったもの。 それでも君は、ふわりといつもの柔らかな笑顔を向けて、ありがとうって言ってくれた。 その瞬間に、すっとその目から弱い君は消えて、代わりに強い意志が光る。 「いってきます」 君は軽いキスをおでこに一つ残して、またにこりと笑った。 そのまま君は私に背を向けて行ってしまった。一度も振り返らずに。 君の触れた箇所がほんの少し熱い。 君が残したものを握り締めて、私はぐっと唇を噛んだ。 「いって、らっしゃい」 小さくてか細い私の声は、冷たいつめたい風にさらわれて消えた。 君の背中が見えなくなってから、私も君に背を向けた。 君が居なくなった次の朝、君が残した鍵を使って君の家に行った。 一歩、足を踏み入れたら君の匂いがふわりと私を包んで、不覚にもじわりと目が熱くなった。もう一歩、もう一歩、進む度に君を感じて、目の前が歪んで滲む。 じわりじわりと実感する、私の中の君という大きな存在。 近くに君がいない現実と寂しさ。会いたいのに会えない辛さと苦しさ。 自然と嗚咽が漏れた。ぼろぼろと涙が零れ落ちて床にシミができる。 小さい子みたいに声を出して、たくさんたくさん泣いた。 心臓がぎゅってなって呼吸がうまくできなくて、早く君に会いたいって痛いくらいおもった。会いたい。会いたい。会いたい。会いたい。会って名前を呼んで手をつないで抱きしめてキスをして。でも今は何一つできなくて。 また心臓がぎゅって苦しくなって呼吸ができなくなった。 このまま君がいない日が続くなんてって考えたら、私はいつか死んでしまう、そんな馬鹿馬鹿しいことを自分のわがままでいっぱいの頭の中でおもった。 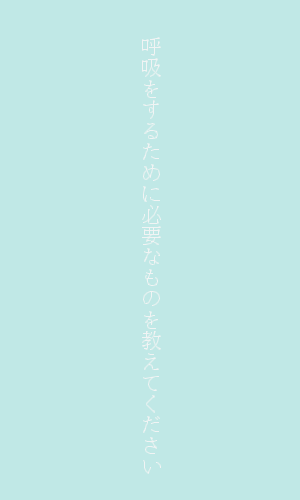 |